| 22 | “Ⅱ 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|
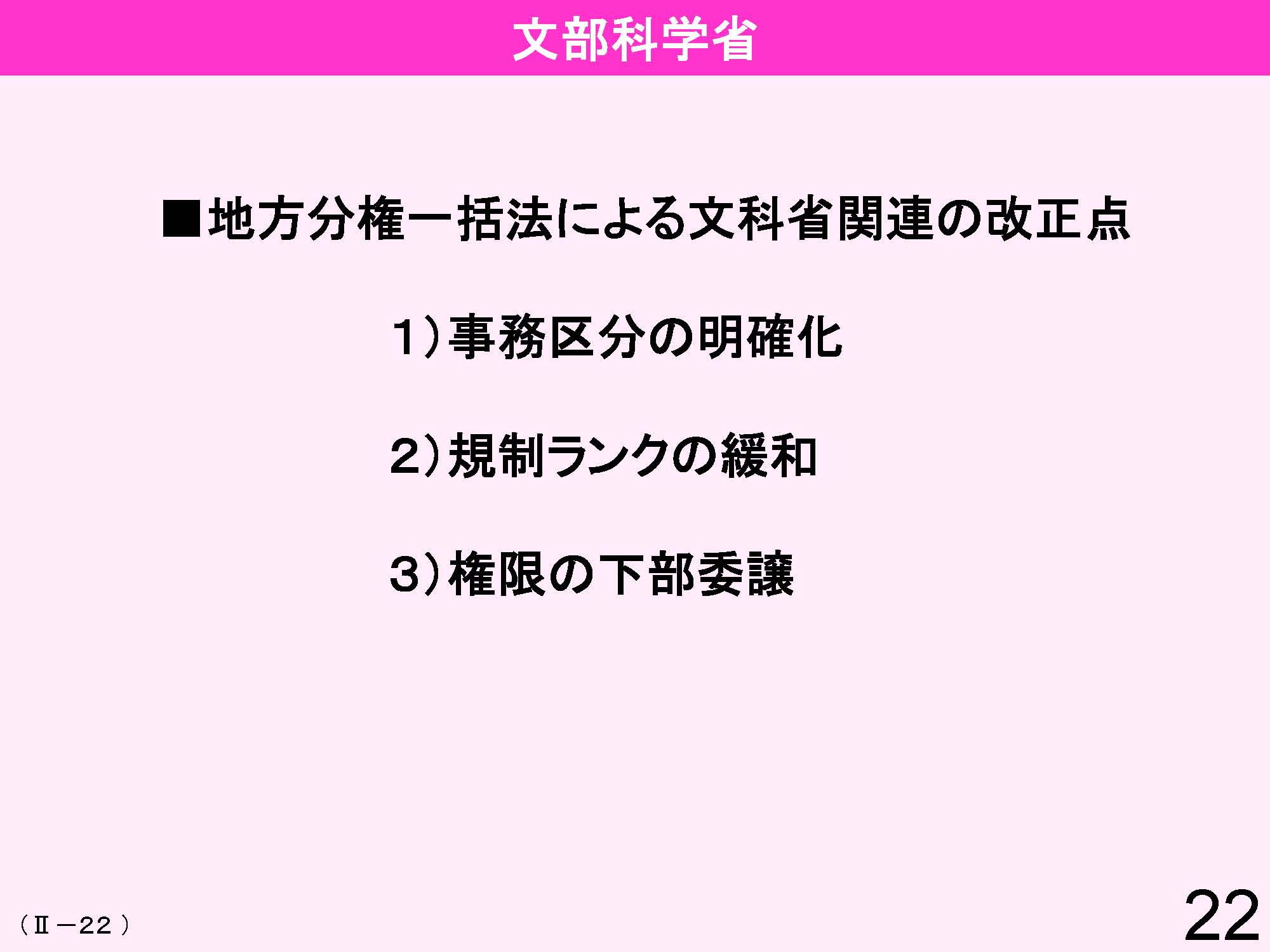 |
||||
| 1999年地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)を受けて、特に地方との役割の見直しで課題となった点に焦点づけて説明。1999年に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(略称:地方分権一括法)により、23省に渡り計475本の法律が改正された。文部省関連の改正では、20の法律と1つの政令が改正された。それらの要点を整理すると以下のようになろう。
1)事務区分の明確化 学校教育法第106条を削除して「監督庁」を明確化。その他、ここには私立学校振興助成法第17条において法定受託事務が明確化されたことも含まれる。 2)規制ランクの緩和 例えば、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第4項中「一般的指示を行う」との規定を「技術的な基準を設ける」に、第48条第1項中「行うものとする」を「行うことができる」に、あるいは公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第5条の「認可」を「協議と同意」に改められている。 3)権限の下部委譲 例えば、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で教育長の任命承認制を廃止したり、第58条第1項で県教委による指定都市教委への「委任」を廃止し、第61条第1項で中等教育学校に関する権限の「委任」を廃止するなどの規定が盛り込まれた。 |
||||
この教材に関する質問・意見はこちらへどうぞ
kamada@criced.tsukuba.ac.jp
筑波大学教育開発国際協力研究センター(CRICED)
〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1